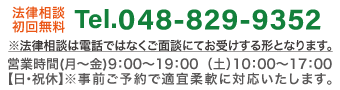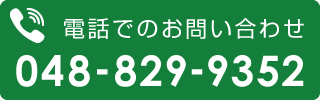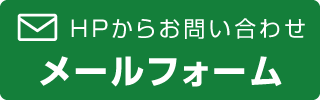Author Archive
【お知らせ】高次脳機能障害、脳脊髄液減少症、椎間板ヘルニア等
当事務所では、交通事故、労災事故、自転車事故、その他日常生活における事故における人身損害の賠償問題のうち、「因果関係」が争点となる事案についても積極的に受任しています。
とくに、高次脳機能障害、脳脊髄液減少症、椎間板ヘルニアなどの傷病名がついた事案では、相手方が因果関係を否認したり、逸失利益を限定的に捉えたりするなどして、賠償の一部または全部を拒絶することがあります。
「因果関係」というキーワードが出てきたら、まずは、弁護士までご相談下さい。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【法律コラム】相続:預貯金は遺産分割の対象か?
銀行預金が遺産分割の対象になるか否かが争われた裁判で、最高裁大法廷が、先月19日、両当事者の意見を聞く弁論を開きました。
従来から、最高裁は、預貯金を遺産分割の対象とせず、不動産や株式といった他の財産と関係なく、法定相続分に応じて当然に分割されると考えてきました。つまり、相続人同士で、遺産分割協議が整っていなくても、早く預金の払戻しを受けたい相続人は、銀行等の金融機関に対して、法定相続分にしたがった預金の払戻しを求めることができる、というのが現在の正しい理論です。
ところが、現実問題として、上記理論にしたがって、遺産分割をしないまま各相続人が金融機関に対し払戻しを求めても、金融機関は、相続人同士の争いに巻き込まれることを避けるため、遺産分割協議書か、相続人全員の同意がなければ、法定相続分の預金の払戻しには応じていません。その結果として、弁護士が代理人となって粘り強く交渉するか、あるいは、銀行に対し訴訟を提起することが必要となっています。
上記のような現実問題に対応する形で、弁護士同士の話合いや家庭裁判所における調停などでは、預貯金も遺産分割の対象とするなど、柔軟な解決を試みていました。
最高裁の判例が変更になり、預貯金も遺産分割の対象とすることになれば、社会における一般的な感覚や銀行実務に近い形となり、相続財産の公平な分配を実現することが可能になると思われますが、遺産分割が成立するなど相続人同士で一定の合意が成立しなければ、預金の払戻しを受けることがおよそ困難になります。その結果として、紛争(払戻しができない状態)は長期化し、相続税の申告期限である10か月以内に遺産分割協議が成立せず、相続税を納税するための資金を用意できないという可能性も出てきます。
実務的に非常に重要な判例となるため、今後も注目していきたいと思います。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【お知らせ】10月24日(月)25日(火)は臨時休業します。
10月24日(月)、25日(火)は、終日、臨時休業いたします。
メール、お問合せフォームよりご連絡いただければ、26日(水)に折り返しご連絡させていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【雑感】~弁護士増員時代に思うこと~
こんにちは。弁護士の坂根です。
本日は、法律の話ではなく、思うまま書こうと思います。
現在、全国の弁護士の人数は、約37,000人で、関東の分布は以下のとおりです(日弁連HPより)。
東京 約17,500人
神奈川 約1,500人
埼玉 約800人
千葉 約750人
群馬 約270人
茨城 約270人
栃木 約210人
近年、弁護士の人数は増加し続けていますので、弁護士業界における競争は年々激しくなってきています。
多くの法律事務所がテレビ、インターネットなどさまざまな媒体を通じて、広告を強化しており、法律事務所も、一つの会社のように、スタッフを多数雇用し、マニュアルに基づいて、業務を効率的に処理できるようにしています。
他方で、上記のような法律事務所とは異なり、固定客あるいは紹介者がいる方に限定して依頼を受けている、従来型の法律事務所もたくさんあると思います。
さまざまな形がある中で、私も日々模索しながら、ひとまずは目の前の案件に注力していますが、1つだけ強く感じていることがあります。
それは、弁護士の仕事は、発想や創造がとても大切で、「考えて」「悩んで」「生み出す」という過程を簡略化することはできないということです。
イメージでいうと、皆さまが法律問題を解決して再び次のステップへ走り出せるように、そのための「走りやすい靴」を、弁護士が一から設計して、デザインして、材料を選び抜いて、自分で製造までやって・・・履いていただくという感じです。だから、そういう意味で、設計から製造までをやる、一種の「職人」です。
日中は来客対応で、上記のような考える時間をとることが難しいため、帰宅時間も遅くなってしまいがちです。
思うままに書いてみましたが、また、このような雑感も発信していけたらと思います。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【法律コラム】交通事故:後遺障害等級について理解する
こんにちは。弁護士の坂根です。
本日は、交通事故に関する法律コラムです。
前回は、後遺障害等級について総論的な事項をご案内しました。
本日は、各論に入りたいと思います。
交通事故における後遺障害等級は、あくまで損害賠償額を算定するための資料として決定されます。
そのため、1級から14級、そして各等級ごとにさらに細かく〇号~〇号というように類型化されています。
これらの類型にあてはまらない症状は、基本的に、医学的な意味の後遺症であったとしても、基本的には、交通事故の後遺障害等級としては認定されません(もっとも、高次脳機能障害などの事案において、〇級相当という形で認定されることもあります)。
交通事故の後遺障害等級に類型的に当てはまる代表的な症状として、以下の症状が挙げられます。
① 神経症状(痛み、痺れ、麻痺など)
② 骨折後の関節可動域の制限(手首や足首の可動域が狭くなったなど)
③ 外貌醜状(顔などに傷跡が大きく残ったなど)
④ 複視、視力低下など
⑤ 高次脳機能障害
後遺障害等級が認定されると、損害賠償額が高額になりますので、①から⑤までのいずれのケースも保険会社との間で金額に関する見解の相違が大きくなります。
最近では、医学的に注目されていることと相俟って、とくに⑤の高次脳機能障害のケースが非常に問題となることが多く、解決までにさまざまな法的問題をクリアしなければなりません。具体的には、事故との因果関係、障害の程度や内容、後遺障害等級の妥当性、等級認定後の損害賠償金の妥当性などが問題となります。
交通事故の賠償問題は、弁護士に依頼して解決すべきであると考えておりますが、後遺障害等級が認定された事案では、安易に示談すると被害者の方の損失が大きくなってしまうため、よりいっそう弁護士による正しい解決が求められます。
次回は、各後遺障害についてもう少し掘り下げていきます。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【お知らせ】新しい弁護士活用法~当事者による紛争解決~
こんにちは。弁護士の坂根です。
ずいぶんと秋らしくなってきましたね。今年も早いものであと3か月です。
さて、本日は、少しいつもとは違ったご案内をしたいと思います。
ご相談を日々お受けしていると、弁護士に依頼することをためらってしまう方がいらっしゃいますが、その理由の1つに、「弁護士に依頼して戦うほどもめたくない」という点があるようです。
たしかに、一方の当事者に弁護士が就くと、他方の当事者にも弁護士が就くことが多く、その結果として、紛争解決が長引くことも多いのが現状です。また、互いに弁護士に依頼して戦うとなると、相続などの事案では、親族間同士の関係がよりいっそう破綻してしまうという事情もあります。
こういった事情の中で、原則として当事者同士で解決することを前提に、適宜、必要に応じてアドバイスを受けたい、後方支援をしてほしい、といったご要望があります。
当事務所では、このようなご要望にお応えするため、裁判外の任意交渉が可能な事案に限定して、弁護士が前面に出る代理交渉ではなく、法的知識のご説明、交渉方法のご案内など後方支援を目的とする、弁護士活用法をご案内できるようにしております。
相続の事案などではご利用しやすいと思います。
ご興味のある方は、一度当事務所までご相談下さい。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【法律コラム】交通事故:どの程度で後遺障害は認められるのか
こんにちは。
弁護士の坂根です。少しずつ秋らしい季節になってきました。
さて、今回は、しばらくお休みしていた交通事故に関するコラムです。
これまで、治療→症状固定→後遺障害申請の方法などについてお話してきました。
今回は、損害賠償金の金額を決定づける後遺障害について説明したいと思います。
まず、「後遺障害」とは何でしょうか。
一般的には、自動車事故による障害と症状との間に相当因果関係があり、かつ、将来においても回復が困難と見込まれる精神的又は身体的なき損状態であって、その存在が医学的に認められるものと定義されています。
しかし…非常に難解な定義づけである上、あいまいで抽象的でもあります。
そのため、ご相談者の方には、後遺障害と社会保障における身体障害を混同して、「自分の症状はとても後遺障害といえるほど重篤なものではないでしょう」とお考えになる方もいらっしゃれば、他方で、「症状が残っているのになぜ後遺障害が認定されないんだ」とお考えになる方もいらっしゃいます。
そこで、あえて大胆に、後遺障害等級の認定における、わかりやすい目安をご案内すると以下のとおりです。
① 後遺障害の要件である「将来においても回復が困難」といえるためには、概ね6か月以上の治療を要したことが必要である。
② 6か月未満の治療で終了した場合、「将来においても回復が困難」と評価できないため、後遺障害等級は認定されづらい。
③ 6か月以上の治療を要したとしても、月数回程度の通院治療や整骨院中心の治療であった場合には、後遺障害等級は認定されづらい。
④ 骨折等がなく、痛み・しびれといった自覚症状が中心であっても、後遺障害等級(14級)は認定される。
⑤ 年齢性の所見があっても、病的な既往症でない場合には、むしろ痛みの客観的証拠として捉えられ、交通事故による後遺障害として評価されうる。
⑥ 手足の可動域の制限に関する後遺障害等級は、通常、受傷時の骨折や腱断裂などを前提としている。
⑦ 高次脳機能障害に関する後遺障害等級は、通常、受傷時の脳挫傷などを前提としている。
以上、ざっと指摘しましたが、上記は公表されている公式の基準などではなく、私の考え方です。
後遺障害等級に関するご相談は、事故状況や過失割合と並んで、非常にご相談が多い分野です。
わからないまま手続きを進めず、一歩立ち止まって弁護士にご相談することをお勧めします。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【お知らせ】ご相談及びご依頼のご対応状況
こんにちは。
弁護士の坂根です。
前回更新からだいぶ期間が空いてしまいました。
お盆明けより新規のご相談等が多くなり、また、手持ち案件が増加してきたこともあり、多忙な日々が続いております。
非常に幅広い分野のご相談をいただいておりますが、弁護士に相談すること自体にハードルの高さを感じている方が非常に多いと思われます。
当事務所では、ご相談時に、解決方針をご案内するだけではなく、弁護士費用の観点から、依頼することでプラスになるのか否かという現実的な問題についても、できる限り具体的にご案内するようにしております。
その結果、ご相談者の方が安心してご依頼いただけているように思います。
交通事故、労働問題、相続、債権回収、訴訟対応全般を取り扱っております。
不安をお感じになられた方は、できる限り早急に、ご相談される方をお勧めします。
みなさまのご連絡、お待ちしております。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【法律コラム】交通事故:症状固定と後遺障害(2)
こんにちは。
弁護士の坂根です。
本日も、交通事故における症状固定以降の問題を取り上げていきたいと思います。
症状固定時点で強く症状が残っている場合、後遺障害申請を行うことになります。
ここにおける後遺障害申請とは、あくまで自賠責保険における後遺障害等級を認定するための手続を指しますので、障害者手帳における等級などとは異なります。
後遺障害の症状に応じて、1級から14級までのレベルが設定されており、これらの等級が損害賠償金の算定指標となっています。
後遺障害申請の方法には、「事前認定手続」と「被害者請求手続」の2パターンがあります。
加害者の自動車保険に任意保険が付帯していて、治療費なども含めて任意保険会社が支払っている場合、任意保険会社が治療状況を把握し、かつ、診断書や診療報酬明細書等の資料も取り付けているため、被害者は、病院で後遺障害診断書の作成を受け、これを任意保険会社に提出することのみで後遺障害申請を行うことができます(事前認定手続)。
他方、加害者の自動車保険に任意保険が付帯していない場合や付帯していても治療費の対応を行っていない場合などは、被害者が事故から症状固定までの診断書、診療報酬明細書、レントゲン、CT、MRI等の画像資料を準備の上、自賠責保険会社に請求書類を提出することによって後遺障害等級認定を受けます(被害者請求手続)。
事前認定手続と被害者請求手続のいずれであっても、申請に必要な資料を受領した任意保険会社や自賠責保険会社が、損害保険料率算出機構の下部機関である自賠責損害調査事務所に後遺障害の審査を委嘱して、そこで実質的に等級を認定することになりますので、基本的に、結論に大きな相違が生じることはないと考えられます。事前認定手続の場合、形式的には、「任意保険会社が認定した」という形がとられますが、任意保険会社は、自賠責損害調査事務所で出た結論を尊重しますので、やはり結論に大きな相違が生じることはないと考えられます。
もっとも、示談交渉の相手方である任意保険会社が、被害者の後遺障害等級認定の実務に関与することに一定の不信感や抵抗感のようなものがあって、かつ、被害者の方が早期に自賠責保険部分の賠償金を受領したい場合には、被害者請求手続を利用する必要があります。
当事務所では、原則として、被害者請求手続を利用していますが、さまざまな事情を考慮の上、事前認定手続を利用することもあります。
交通事故のご相談は、初回無料です。
後遺障害申請についてご不明な点がございましたら、ぜひ一度当事務所までご相談下さい。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【お知らせ】当事務所の取扱分野について
こんにちは。
弁護士の坂根です。
みなさまよりご相談のお問合せなどをいただく際に、「~の分野は取り扱っていますか」といったご質問をいただくことが多いので、当事務所における取扱事件の特徴をご紹介します。
以前にも少しご案内しましたが、主として、以下のような内容となっています。
① 交通事故(被害者側)
② 労働問題(残業代、不当解雇)
③ 相続(遺産分割協議、相続登記、遺言など)
④ 不動産問題(オーナーや不動産業者様からのご相談)
⑤ 会社や個人事業主の方からのご相談(債権回収、契約書作成など企業法務全般)
⑥ その他日常生活における法律トラブル
もちろん、上記以外のご相談もお受付していますので、まずは当事務所までご連絡いただければと思います。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。