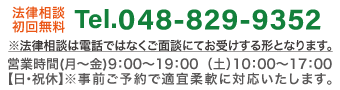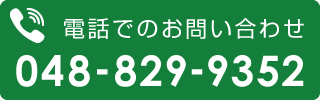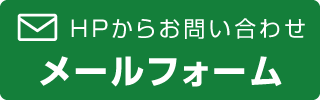Author Archive
【お知らせ】弁護士による後方支援を受けたい個人の方へ
こんにちは。弁護士の坂根です。
1年でもっとも寒い季節になりました。
寒さに負けず、皆さまからのご相談やご依頼に対し、熱く熱く対応できるよう気持ちを入れて日々取り組んでいます。
開業して約10か月を経過しましたが、当事務所の取扱事件は、交通事故、相続、労災事故、労働問題(残業代、解雇)、債権回収、企業間あるいは企業対個人の損害賠償請求事案、中小企業の法律顧問など非常に幅広く、訴訟案件も増加しています。
また、従来型の法律事務所ではあまりないと思いますが、当事務所では、個人の方の法律問題について、必ずしも弁護士間交渉や裁判による解決を望まない方を対象に、後方支援を目的として、顧問契約を締結し、定期的なご相談に対応しています。事案によってはご依頼を受けられない場合もありますが、全体として、このような形でのご依頼も増加しています。料金設定はさまざまですが、ご相談内容に応じてリーズナブルな料金をご案内できるようにしていますので、ご興味のある方は、当事務所までご連絡下さい。
まずは、お気軽に無料相談をご利用いただければと思います。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【お知らせ】交通事故・損害賠償金の提示を受けた方へ
こんにちは。弁護士の坂根です。
当事務所は、交通事故の賠償事案に積極的に取り組んでおり、最近では、事故直後あるいは事故後早い段階で、ご相談やご依頼をお受けしていますが、他方で、「保険会社から損害賠償金の提示を受けたが、慰謝料や逸失利益の金額に納得ができない。保険会社から提示された金額は妥当か。弁護士に依頼すれば増額できるか。」といった趣旨のご相談も多いといえます。
通常、弁護士費用特約をご利用できない方につきましては、損害賠償金から弁護士費用をいただく形となりますが、事案に応じてご依頼いただきやすいように工夫して弁護士費用を設定しています。
すなわち、上記のようなご相談者の方は、「すでに提示されている損害賠償金は最低限、自分に対する補償分として確保したい」「その金額を割り込む形で弁護士費用を負担するとすれば、事実上、費用倒れになるから不安だ」とお考えになると思いますので、このようなご意見を踏まえ、事案や増額の可能性にもよりますが、「すでに提示されていた金額から伸びた金額(増額部分)の〇%」というような形で弁護士費用を設定しています。このような費用設定であれば、「弁護士費用を支払うことにより、当初の金額を下回ってしまうことは通常存在しない」ため、比較的ご依頼いただきやすいと思います。
弁護士費用の基準につきましては、初回無料相談時にご案内を差し上げるようにしておりますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【法律コラム】交通事故:後遺障害診断書の書き方(5)
こんにちは。弁護士の坂根です。
さて、本日は、「後遺障害診断書の書き方」について最後のご案内となります。
後遺障害診断書の右側の最下部に、「障害内容の増悪・緩解の見通しなどについて記入して下さい」と記載されていますので、医師は、この欄に、症状に関する今後の見通しを記載することになります。
通常は、「症状固定と考える」とか、「緩解の見込みはない」などと記載されますが、原則として、この欄の記載が後遺障害等級の決定的要素になることはありません。
もっとも、推測になりますが、むち打ち損傷などで、後遺障害14級が認定されるかどうか微妙で、おそらく当落線上にあると思われる事案について、この欄に、「少しずつよくなる」といった趣旨の記載があると、ときに、等級判断の理由中に「『少しずつよくなる』という記載もあることから、将来においても回復が困難とはいえない」という形で指摘、引用され、非該当の理由の一つとなってしまうことがあります。本当に「少しずつよくなる」のであれば、その記載でもよいとは思いますが、見通しが不明なものについては、そのようなニュアンスの記載はできれば避けたいところです。
次回からは、別のテーマでお話したいと思います。
コラムに関するリクエストなどがあれば、既存のご依頼者様、新規のご相談者様、その他どなたでも構いませんので、お問合せフォームからご連絡下さい。できる限りご対応できるよう頑張りたいと思います。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【法律コラム】交通事故:後遺障害診断書の書き方(4)
こんにちは。弁護士の坂根です。
本日も、前回に引き続き、後遺障害診断書の書き方についてご案内していきます。
これまで、「自覚症状」欄、「他覚症状および検査結果」欄についてお話してきましたが、今回は、「関節機能障害」欄(後遺障害診断書の右下)について触れたいと思います。
たとえば、右手首骨折後、骨は癒合したものの、右手関節が曲がりづらくなった場合、「関節機能障害」の欄に、左右の手について関節の可動域(曲がる角度)を記載することになります。
後遺障害等級の認定方法は、健肢(けがをしていない方)と患肢(けがをした方)の角度の「差」で決まります。自動値(自分で曲げる)と他動値(医師が曲げる)がありますが、等級認定は、他動値の「差」に基づいて行います。
上記の右手首骨折の場合でいえば、左手関節の可動域と右手関節の可動域を比べることになりますが、測定時に、左手関節をしっかりと曲がる範囲だけ曲げないと、右手関節の可動域との「差」が小さくなるため、後遺障害が非該当になったり、軽度の等級になったりしてしまいます。また、怪我をした右手関節についても、無理をして必要以上に曲げてしまうと、「よく曲がる」ということになってしまいます。あまり意識しすぎる必要はありませんが、原則として測定し直すことはできませんので、上記のような理屈を知っておく必要があります。
測定時の体調やちょっとした気持ちの違いで、測定結果にバラつきや矛盾が生じることがあるため(たとえば、治療中にも可動域を測定していたが、症状固定時の測定結果の方が可動域が狭く、症状として悪化しているなど)、因果関係や等級について裁判などにおいてもよく問題となります。すでに、関節の可動域やその等級を巡って疑問点があったり、あるいは、すでに争いになっている場合は、できる限り早めにご相談下さい。
次回は、「障害内容の増悪・緩解の見通し」欄についてご案内したいと思います。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【法律コラム】交通事故:後遺障害診断書の書き方(3)
こんにちは。
本日は、昨年末に続き、交通事故における後遺障害診断書の書き方についてご案内したいと思います。
本日は、後遺障害診断書のうち「他覚症状および検査結果」欄について触れていきます。
まず、この欄には、文言どおり、「他覚症状」=画像(レントゲン、MRI、CT)上の所見を記入する必要があります。後遺障害申請を行う際、自賠責保険会社や自賠責調査事務所に対し、治療中に撮影した画像をCD-Rなどで提出し、後遺障害調査はそれらの画像に基づいて行われることになりますので、画像上の所見について多少の記載漏れ(言及漏れ)があったとしても、それのみで「所見なし」ということにはなりませんが、やはり、主治医の診断はとても重要ですので、画像上の所見については詳しく書いてもらう必要があります。
この場合の所見とは、頚椎捻挫や腰椎捻挫であれば、頚椎や腰椎の変性所見やヘルニア、骨折等がある場合には骨折箇所の骨癒合の状況、腱の損傷等がある場合にはその損傷具合等を指します。
具体的な記載については主治医の判断に委ねることになりますが、交通事故による外傷性所見であると断定できなくても(=因果関係が不明であっても)、「自覚症状」欄に記載した症状の原因となりうるものであれば、もれなく所見を記載してもらう必要があります。
また、患部を触ってその反応を確認する検査(知覚、反射)や患部付近の筋力や筋萎縮などを測定する検査を実施した場合には、その結果も記載する必要があります。もっとも、異常がなければ、記載する必要はありません。
当事務所では、被害者の方が医師に後遺障害診断書の記入をお願いしたものの、不十分な内容である場合は、別途、医療照会を行うことにより、補足することがあります。
次回は、「関節機能障害」の欄についてご案内したいと思います。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【ご挨拶】本年もどうぞよろしくお願い申し上げます
こんにちは。弁護士の坂根です。
新しい1年が始まりました。皆さま、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
早いもので、弁護士8年目の年になりました。新しいことにも挑戦していく所存ですが、私が弁護士として「たいせつにすること」は毎年同じです。
それは、ホームページ上の当事務所の理念でも謳っておりますが、下記の5つです。
① ご依頼者様との信頼関係の重視
② 迅速な対応
③ わかりやすい説明
④ 弁護士費用の明確化
⑤ ご依頼者様のニーズに沿う解決方法のご提案
今、このコラムをご覧になった方は、「どこの法律事務所のホームページでも書いてあるような…」とお思いになるかもしれませんが、この5つは、とてもとても大切で、初回のご相談から事件の解決まで私が常に心掛けていることです。
とくに、①③は、ご依頼者の方に「安心」を与えるものですので、今後もできる限りの工夫をしていきたいと思っています。
すでにご相談やご依頼をいただいている方も、相談しようか悩んでいる方も、ご不明な点がございましたら、ぜひ一度当事務所までご連絡下さい。
また、大変嬉しいことに、過去にご依頼いただいた方からのご相談やご紹介も多数いただいております。当事務所までご連絡いただければ直接私が対応させていただきますので、ご遠慮なくお問合せ下さい。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【法律コラム】交通事故:後遺障害診断書の書き方(2)
さて、本日も、後遺障害診断書の書き方についてご案内していきます。
前回は、「自覚症状」欄については、病院の先生に「できる限り詳細に」、かつ、「漏れなく」、記載してもらう必要があることをお話しました。
後遺障害診断書は、基本的には病院の先生の裁量で作成してもらうため、あまり細かな点まで指示したり、お願いしたりすることはできませんが、実務上、以下のようなポイントがあります。
・「ときどき痛む」、「~の際に痛む」→平時は痛みが(あまり)ないといった解釈をされてしまい、後遺障害等級非該当の理由とされることがある。
・「軽度の痛み」→文字どおり、「軽い」と評価されてしまい、後遺障害等級非該当の理由とされることがある。
・「軽減したが、なお痛む」→「痛む」の方に比重があるとしても、自賠責調査事務所(後遺障害の調査をする機関)は、「軽減」という文言に対しては非常に敏感であるため、「軽減」という記載が後遺障害等級非該当の理由とされることがある。
・受傷部位から到底、派生し得ないような症状の記載がある→因果関係がないものとして、後遺障害等級非該当の理由とされることがある。
次回は、「他覚症状および検査結果」欄について、私なりの考え方を述べたいと思います。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【法律コラム】交通事故:後遺障害診断書の書き方(1)
こんにちは。弁護士の坂根です。
久しぶりに、交通事故についてお話したいと思います。
今回は、タイトルのとおり、後遺障害診断書の書き方についてご案内したいと思います。
後遺障害診断書の記載事項で、よく問題となる項目は、主として以下の4つです。
1 「自覚症状」の欄
2 「他覚症状および検査結果」の欄
3 「関節機能障害」の欄
4 「障害内容の増悪・緩解の見通し」の欄
本日は、1の「自覚症状」についてご説明します。
むち打ち損傷等により頚部、腰部、手足などに痛みやしびれなどの神経症状が残った方については、「自覚症状」欄の記載が非常に重要です。
なぜ重要かといいますと、神経症状に関する後遺障害の等級認定は、「自覚症状」欄に記載された症状ごと(部位別)に、等級の該当性を検討するからです。
つまり、「自覚症状」欄に複数の症状が記載されていて、部位も複数に渡る場合、原則として、それらの症状は部位別に等級の該否を検討してもらえるため、相対的に等級認定の可能性が高くなります。
また、複数の症状が「頚部の痛み」「めまい」「右手指の痺れ」などと漏れなく記載されている方が、ただ一言「頚部の痛み」と記載されているより、程度として重い症状であると評価できると思います。
他方、本来は症状があるのに、その症状が記載されていないと(例えば、頚部痛のほか腰痛もあるのに、腰痛に関する記載が漏れている場合)、その症状(腰痛)は「存在しないもの」あるいは「治癒したもの」として取り扱われますので、この場合、当然のことながら、記載漏れの症状について後遺障害等級は認定されません。
ちなみに、異議申立てを行う際などに、あらためて症状を加筆してもらったり、別途診断書等を用意しても、後から生じた症状として取り扱われる可能性が高く、因果関係がないものとして、等級認定の対象に至らないことが多いといえます。
したがって、とくに痛み、痺れなど自覚症状を複数有する方は、病院の先生に、できる限り詳しく、漏らさず症状を記載してもらうことがとても大切です。
次回も、後遺障害診断書の書き方について、ご案内していきます。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【お知らせ】年末年始の営業について
年末年始は、下記のとおり、12月29日(木)から1月3日(火)までお休みをいただきます。その前後は通常営業です。
【年末年始スケジュール】
12月28日(水)まで 通常営業
12月29日(木)~1月3日(火) 休み
1月4日(水)より 通常営業
メールやお問合せフォームからのご連絡は可能ですが、お返事が休み明けとなりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【お知らせ】12月2日(金)3日(土)は休業します。
12月2日(金)、3日(土)は、所用により臨時休業いたします。
メールやホームページのお問合せフォームからのご連絡は可能です。
お返事が週明けとなることにつきましてはご了承下さい。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。